短期連載:スタートアップの古都、京都を訪ねる
ハードウェアこそが、日本が世界で戦える武器になる——Makers Boot Campの挑戦
 写真提供:Makers Boot Camp
写真提供:Makers Boot Camp
京都府といえば世界に誇る観光都市として有名だが、任天堂、日本電産 村田製作所、京セラ、オムロン、ロームといった時価総額1兆円を超える企業が6社あり、都道府県別でみた大学数でもトップ10に入るなど、ものづくり人材に恵まれた街でもある。そんな京都がIoT以降のハードウェアスタートアップを輩出する台風の目になるかもしれない。
※Makers Boot Campは2020年にMonozukuri Venturesに名称を変更していますが、本稿では掲載時の名称のまま掲載しています。(※2020年3月7日編集部追記)
「温かい応援ではなく、一緒に新しい知恵を、アイデアを出してほしい」
2018年8月某日、本社のホールに集まった社員の前で島津製作所常務執行役員の稲垣史則氏は、若手社員たちによる新しいチャレンジへの参画を訴えた。
140年の歴史を持つ老舗精密機器メーカーにして、ノーベル賞受賞者を輩出する世界的な企業である島津製作所がスタートアップ向けのファンドに出資したのは2018年7月のこと。それから一カ月後、東京からmoff、no new folk studioという気鋭のスタートアップ2社のCEOを招き、オープンイノベーションを推進するプロジェクトのキックオフイベントが開かれた。
トップダウンだけではない、草の根からの危機感
 島津製作所の社内イベントにはスマートシューズを手がけるno new folk studioの菊川裕也氏(奥から2人目)や、ウェアラブルデバイスを活用したリハビリ支援ソリューションを開発するmoffの高萩昭範氏(中央)ら、ハードウェアスタートアップのCEOを招いた。
島津製作所の社内イベントにはスマートシューズを手がけるno new folk studioの菊川裕也氏(奥から2人目)や、ウェアラブルデバイスを活用したリハビリ支援ソリューションを開発するmoffの高萩昭範氏(中央)ら、ハードウェアスタートアップのCEOを招いた。
島津製作所では以前から大学や有望なベンチャーと提携し、共同研究や製品開発を進めてきた。しかし、これまでのような社外との関わり方では時代の変化に対応できないという危機感が上層部だけでなく、前線で働く社員の中にも生まれていた。その一人で、島津製作所でプロダクト UX デザイナー(当時)として勤務する清水耕助氏は2013年から約4年半駐在した中国でスタートアップが生活を大きく変えるさまを目の当たりにした。
「上海での滞在中、それまで全く知らなかったサービスが現れ、1~2カ月の間に人々の生活に浸透していくのを何度も目の当たりにしました。その当時の中国に対する日本の報道は大気汚染や食品の偽装問題が中心だったので、自分なりに中国のスタートアップ事情を調べて社内の仲間にメルマガのような感じで送っていました」
 SHIPSのキックオフイベントで社員のプロジェクト参画を訴えた島津製作所常務執行役員の稲垣史則氏(左)と、Makers Boot Campのミートアップで中国の動向についてピッチした経験を持つ清水耕助氏。イベントには本社に勤務する社員ら100人以上が集まった。
SHIPSのキックオフイベントで社員のプロジェクト参画を訴えた島津製作所常務執行役員の稲垣史則氏(左)と、Makers Boot Campのミートアップで中国の動向についてピッチした経験を持つ清水耕助氏。イベントには本社に勤務する社員ら100人以上が集まった。
清水氏が2017年12月に日本から帰国すると、京都市内にもいくつかスタートアップを支援する拠点や組織ができていて、頻繁に顔を出すようになった。今回のキックオフイベントのきっかけとなったMakers Boot Camp(メイカーズブートキャンプ、以下MBC)も、その一つだ。
その頃、島津製作所ではMBCが運用する試作ファンドへの出資を検討しはじめた段階だった。出資の背景には単純なスタートアップへの出資ではなく、時代の変化に合った事業創出を社内に促したいという強い意志があった。そのためには全ての機能を外部に委ねるのではなく、社員の積極的な参画が不可欠だった。
「当初は自社に眠っている技術や休眠特許をスタートアップに公開するという話も役員同士の議論の中であったのですが、それだけでは面白くないし、やりたい事があって起業しているスタートアップに自社の技術を押し付けるのはどうだろう、という思いもありました。そこで自分なりにアイデアをいくつか出して関係部署の人にメールを送ったところ、回り回って出資の話を担当していた稲垣常務の目に止まり、声がかかりました」(経営戦略室の佐藤道隆氏)
その後、マネジメントクラスの幹部も議論に入った結果、部署横断で集まった若手社員を中心メンバーとして起用し、MBCが持つ外部ネットワークを活用しながら新規事業を創出するプロジェクトを立ち上げることが決まった。
こうして島津製作所はMBCが運営するファンドへの出資を決め、同時にスタートアップとの協業や社内からの新たなアイデア創出を狙うプロジェクト「SHIPS(Shimadzu Innovation Platform with Startups)」がスタートした。SHIPSには開発やデザイン、経営戦略といった部門から有志の若手社員が中心メンバーとして参加。2019年春には外部との共同研究を加速させるための施設も立ち上げる予定だ。
大企業から地場企業まで巻き込むハードウェア特化型VC
 Makers Boot Campの発起人にして、運営会社Darma Tech Labsの代表取締役の牧野成将氏
Makers Boot Campの発起人にして、運営会社Darma Tech Labsの代表取締役の牧野成将氏
島津製作所のオープンイノベーションの火付け役となったMBCはどのような組織なのか。MBCはVCであるDarma Tech Labsが運営するスタートアップの試作コンサルティングプログラムの総称だ。国内外のハードウェアスタートアップに投資し、製造業を中心とした京都の企業等を必要に応じてマッチングし、スタートアップの製品化を支援している。
現在運用しているファンド「MBC Shisaku 1号投資事業有限責任組合」(通称:MBC試作ファンド)は、京都の金融機関や島津製作所のような大企業から募った資金を元に、シードやアーリーステージのスタートアップを中心に投資、彼らの試作開発を京都の中小企業からなる「京都試作ネット」がバックアップしている。試作開発を請け負う中小企業から見ればスタートアップの案件は未払いや資金不足のリスクがあるが、間にMBCが入って開発費用をファンドから捻出し、スタートアップに必要なパートナーを斡旋することで、スタートアップと中小企業双方のリスクを軽減し、ビジネスを円滑に進められるメリットがある。
代表の牧野成将氏は、ハードウェアスタートアップを輩出できるポテンシャルが最も高い地方都市が京都だと確信している。
「東京に一極集中するのではなく、地方からベンチャーを輩出する仕組みができないかと思っていた際に、最適な都市が京都だと思いました。多くの大学があり、任天堂、京セラ、オムロン、日本電産、島津製作所のようなグローバル企業があり、それを下支えする中小企業も多い。ではベンチャーを生み出すために何が足りないのか突き詰めると、それらをつなげる役割を担う存在が足りなかった」
愛知県出身で京都とは縁がなかった牧野氏だが、大学院でベンチャー企業の経営やエコシステムを研究していた時期に京都が持つ可能性に気づく。2005年、大学院卒業後に京都のVCであるフューチャーベンチャーキャピタルに入社し、以降京都での今日に至るまで京都のスタートアップエコシステムの開拓にまい進することになる。
ITではなく、製造業を評価したアメリカの投資家たち
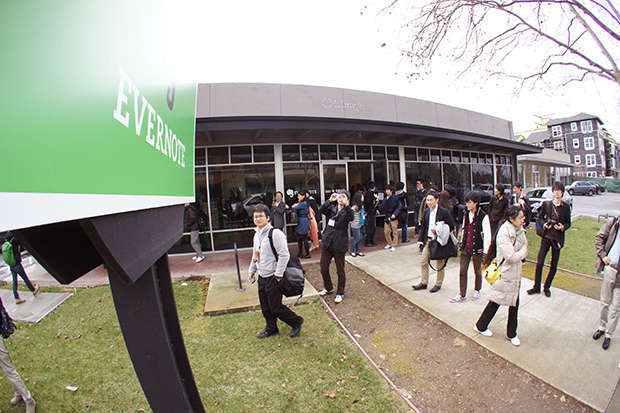 シリコンバレーでは投資前の段階からスタートアップを育成する環境があった(写真提供:Makers Boot Camp)
シリコンバレーでは投資前の段階からスタートアップを育成する環境があった(写真提供:Makers Boot Camp)
2005年当時、国内ではライブドア、サイバーエージェント、楽天といったIT企業が勢いを伸ばし、「ヒルズ族」が流行語になった時期だった。ITベンチャーの大半は東京に集中していたが、関西を含めた地方には東京ほどの勢いを持つベンチャーは皆無に等しかった。
海外に目を向ければGoogleが急成長を遂げ、Facebook、MyspaceといったSNSが世界中で利用されるなど、シリコンバレーはスタートアップのメッカとしての注目を独占していた。国内での勢いに乗じて日本のIT企業も海外に進出するが結果を残せずに撤退、もしくは進出を断念するケースが少なくなかった。Facebookにできて、日本のIT企業が海外に進出できない理由は何か——2007年に牧野氏は自腹を切ってシリコンバレーに渡った。
「シリコンバレーのVCは投資の前段階から育成したりサポートしたりしていて、いわゆるアクセラレーションを大事にしている点が日本と大きく異なることに気づきました。投資するには時期尚早だが可能性があるスタートアップをインキュベーション施設に呼び寄せて育てるという仕組みが機能していて、それがシリコンバレーが有望なスタートアップを生み出す原動力になっていました」
 日本のVCが市場性や成長性を重視するのに比べて、アメリカのVCがテクノロジーを重視することに驚いたという牧野氏。
日本のVCが市場性や成長性を重視するのに比べて、アメリカのVCがテクノロジーを重視することに驚いたという牧野氏。
牧野氏がシリコンバレーの投資家を見て最も印象的だったのはテクノロジーに対する深い探究心と愛情を持っていることだった。
「サービスの移り変わりはあっても、技術は嘘をつかない。これだという技術を持ったスタートアップを応援しようという感覚が当時のVCにはありました」
そんな心意気を持った投資家たちと議論していく中で、ITでは日本はアメリカの後塵を拝しているが、製造業の分野では勝機があることに気づいた。牧野氏は、日本は製造業に固執するがあまりITに乗り遅れたと考えていたが、アメリカの投資家たちが日本に関心を示していたのは製造業の技術力だった。こうして牧野氏は日本の製造業を活用してスタートアップを育成することで、海外での競争に勝てる糸口を見出した。しかし、帰国後すぐにリーマンショックが到来、新規事業ではなく現状の立て直しに奔走することになり、計画が具体化するまでには時間を要した。
再び歯車が動き出したのは2010年ごろ。当時、ハードウェアベンチャーが国内でも活性化しはじめた。そして、同時に多くのスタートアップから量産設計/試作につまずいているという相談が、牧野氏が所属するVCに寄せられた。
「量産設計に困っているスタートアップと京都に拠点を構える老舗の中小企業をマッチングするというアイデアが浮かんだのは、その頃でした。当時、京都試作ネットの代表理事をやっていた竹田さん(クロスエフェクト代表取締役の竹田正俊氏)にアイデアを持ち込んだところ面白がってくれました」
牧野氏はスタートアップの試作/開発のためのファンドを組成し、京都試作ネットが試作を支援するという計画を立ち上げ、2015年8月にDarma Tech Labsを起業した。現在では牧野氏に賛同した企業からの投資を基にしたファンドの運用と、スタートアップの支援を行っている。
 当時、京都試作ネットの代表を努めていた竹田正俊氏。MBCの運営母体であるDarma Tech Labsの共同創設者として経営にも参画している。
当時、京都試作ネットの代表を努めていた竹田正俊氏。MBCの運営母体であるDarma Tech Labsの共同創設者として経営にも参画している。
工場とスタートアップが噛み合わない理由
量産の経験に乏しいスタートアップと、工場や製造業企業との交渉は日本人同士でも簡単にできるものではない。MBCでも当初は両者の噛み合わなさに苦労したという。
「京都試作ネットから見ればメーカーとの取引——言わばプロ対プロでやっていた状況から、プロ対アマに変わったことで生じたギャップは大きかった。仕様書も無ければリテラシーの差も大きい。そういう中で両者の翻訳をするメンバーの必要性に気づきました。幸いにも関西には大手メーカーのOBがたくさんいて、その中には定年退職しても仕事に対するモチベーションが高い人も多かった。そういった経歴を持っている方を採用して、スタートアップのステージや業種ごとに担当を割り振りながら両者の間に入るようにしています」
立ち上げ当初は共同創業者が自らIoTプロダクトの量産化プロジェクトを立ち上げ、実証実験のような形で京都試作ネットに試作/開発を依頼し、発注先の選定やプロジェクトを進める上での勘所など身をもって体験した。
その後、マットの上に載せた在庫品の重量を計測し、残量の計測から発注の自動化まで行うスマートショッピングの「スマートマット」量産化プロジェクトの成功がMBCにとってティッピングポイントになったと牧野氏は振り返る。
「スマートマットを作りたいけど、IT出身でCADもできなければハードウェアのことも分かっていないという状態で相談に来られて、別のところで作った試作品をベースに京都試作ネットと作り直し、18台の量産試作品でユーザーテストを行ったところ手応えのある結果が出ました。そこから資金調達して、量産化までこぎつけることができた。あのプロジェクトは数個の試作品から始まって量産試作と進み、現在では1万台の量産まで進んでいるので非常に印象深いですね」
スタートアップと大企業の連携に教科書は無い
 インタビューはMBCが運営するメイカースペース「Kyoto Makers Garage」で行われた。すぐ近くには京都中央卸売市場があり、このスペースは場外にある空きスペースをリノベーションしたものだ。
インタビューはMBCが運営するメイカースペース「Kyoto Makers Garage」で行われた。すぐ近くには京都中央卸売市場があり、このスペースは場外にある空きスペースをリノベーションしたものだ。
ハードウェアスタートアップを加速させるためには、中小企業だけでなく冒頭の島津製作所のような大企業との連携も必要不可欠だ。MBCにコンタクトしてくる海外のスタートアップ関係者からは、試作だけでなく部品供給や量産、販売まで支援してほしいという相談も多いという。大量生産から販売、アフターサポートまでカバーできる企業の力が求められている状況に対し、中小企業だけでなく大企業も「同じ船に乗る」ことが必要不可欠だと牧野氏は考える。
「私たちの中でも大企業をどのように巻き込むかが大きなテーマになっています。スタートアップとのプロジェクトは必ずしも最初から成功するわけではないので、長く付き合って、事例と知見を積み重ねていかないといけません。京都試作ネットに株主としてMBCに参画してもらっているのは、途中で面倒くさくなって投げ出さないようにするためなんですね。失敗を積み重ねるうちに嫌になって辞められてしまうと、それまで得られたものを台無しにしかねません。私達も実際にこれまでのプロジェクトを通じて、トライ&エラーを重ねてきたからこそノウハウが蓄積できてきたので、大企業にも同様に付き合ってほしい。(MBC試作ファンドに出資した)島津製作所やマクセルにはそうした関係を期待しています」
優れたデバイスを開発したり、世界中のインフラに関わったりしている日本の大企業と関わりたいスタートアップは世界中にいる。人工知能やIoTといった新たな付加価値を提供するスタートアップが大企業と組めば、もたらされる利益は大きいと牧野氏は大企業が参画するメリットの大きさを強調する。
新しい日本の価値を生み出すのは、若い世代の役目
 国際性と多様性を重視するMBCではSNSでの情報発信だけでなく、ミートアップなどの交流イベントも英語を基本としている。(写真提供:Makers Boot Camp)
国際性と多様性を重視するMBCではSNSでの情報発信だけでなく、ミートアップなどの交流イベントも英語を基本としている。(写真提供:Makers Boot Camp)
日本が世界に誇る「ものづくり」のブランドは過去の世代が築きあげたもので、現役世代はそこにあぐらをかいているだけだと、牧野氏は日本が置かれている状況に危機感を覚えている。製造業における経済摩擦で日本がバッシングされたのは遠い昔のこと。現在ではCESなどの国際的な展示会でも存在感が出せず、ピッチコンテストでも存在感をアピールできる日本のスタートアップは非常に少ない。バッシングどころか視野に入っていない現状だ。国際化を前提とした社会の中で、日本は多国籍のチームの中で自分たちの生かせることは何かを追求すべきだという。
「スタートアップの世界はサッカーの世界に似ていて、ナショナルチームの時代は終わって、クラブチーム化してきていると思います。シリコンバレーに行くとアメリカ人だけでなく、アジア、アフリカ、ヨーロッパから来た人も一緒に働いている。一つの国の中から集まった組織と世界中から優秀な人材が集まった組織、どちらが強いかといえば後者だと思います。IoTの世界で言えばインターネットやソフトウェアの領域はシリコンバレーで完結できても、ハードウェアに関しては十分にプレーヤーをそろえられていない。日本が戦えるチャンスはハードウェア、とりわけ量産試作にあると思います」
日本だけでなく海外の市場に対して、試作という武器で打って出る。そのためには京都に限らず、日本全体でハードウェアスタートアップを加速させるためのエコシステムを構築しなければならないと考えるようになったという。
「当初、掲げていたのは京都をハードウェアスタートアップの都にしようということで、京都試作ネットや京都の企業の方々に応援してもらってきました。今は試作に対してファンドで支援するというところから始まり、アイデアから試作を始めるというところでメイカースペースを立ち上げ、量産化に向けても実績が出始めている。そうやって動き続けてきていくにつれて、京都だけでなく日本全体を巻き込んでいくことも考えています」
MBCでは既に浜松市や盛岡市の中小企業との連携を始めていて、今後も提携地域を広げたい考えだ。一方で大企業との連携も加速させたいが、トライ&エラーを重ねていくにあたって一気に広げていくことはマイナスになりかねない。当面はコンパクトに連携できる京都で経験を積み重ねながら、エコシステムの広げ方を模索したいと牧野氏は考える。
 MBC関係者やスタートアップ関係者に牧野氏について尋ねると、「辛抱強い人」だと異口同音に誰もが評する。
MBC関係者やスタートアップ関係者に牧野氏について尋ねると、「辛抱強い人」だと異口同音に誰もが評する。
京都だけでなく、日本全体をハードウェアの聖地にできるか。牧野氏率いるMBCのチャレンジは続く。

