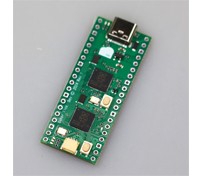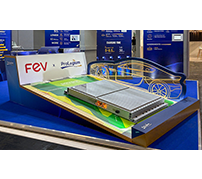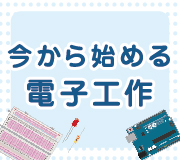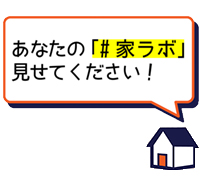筑波大学発スタートアップ
下肢障害者のための立って乗る車いす「Qolo」はモビリティが持つ「自由さ」を体現する

人はいろいろな理由で車いすを使う。手術後など一時的に使うだけの場合もあるが、事故による脊髄損傷、脳卒中など病気による体のまひ、加齢による筋力の衰えなどで日常的に乗らなければならなくなるケースも少なくはない。車いす中心の生活を送る下肢障害者に「立ち上がって生活する自由」を届けるべく「立って乗る車いす」を開発する筑波大学発スタートアップ、Qolo株式会社の代表取締役 江口洋丞(えぐち ようすけ)氏にインタビューを行った。(撮影:加藤タケトシ)
足が不自由な人が立って車いすに乗るのはなぜか
以前fabcrossで、足でこぐ車いす「COGY(コギー)」を紹介した。その時は「足が不自由な人が乗るはずの車いすを、どうして足でこぐのか」という疑問が出発点だった。今回、立って乗る車いす「Qolo(コロ)」を見て湧いた疑問は、「座っていれば楽なのに、どうして立って乗るのか」だ。
その疑問に対して江口氏は、「足が不自由だからといっても、座りっぱなしでいることはデメリットがものすごく大きいから」だと話す。
 Qolo代表取締役 江口洋丞氏。
Qolo代表取締役 江口洋丞氏。
デメリットの大きなものの1つは、血の巡りが悪くなってしまうことだ。例えば飛行機などの狭い座席で長時間同じ姿勢でいると、たいていは居心地が悪くなって無意識にモゾモゾと体をずらしたりするだろう。しかし下肢がまひしている人は、居心地が悪いという感覚もなければ足を動かす筋肉も使えないため、それができない。すると、うっ血して血液が固まり、血栓や褥瘡(じょくそう=床ずれ)を起こしてしまうことがある。
デメリットの2つ目は、骨が弱くなってしまうこと。骨に応力がかからない状態が長く続くと、どんどんもろくなってしまうのだ。そのため、他の人や機械の力を借りてでも「立った姿勢」になることは、骨に力をかける意味でとても大事なことなのだ。
その他にもさまざまな理由から、足が不自由であっても定期的に立ち上がることが良いとされている。しかし何年も、毎日それを継続するのは簡単なことではなく、骨折や床ずれで入院を繰り返す人が少なくないという。
立ち上がることの健康面/機能面/精神面への好影響
健康を維持する以外にも、「立ち上がること」は身体機能や精神面にも貢献する。
身体機能への貢献とは、例えば立ち上がったほうが視界が広がる、高いところに手が届くなど、活動の自由度を高めるという意味だ。立ったままで無理なく動き回れるようになれば日常生活を送る上で行動範囲も広がるし、就労の機会が増え、できる仕事の幅を広げることにもなる。
精神面への貢献というのは、人としての尊厳を守るということだ。車いすに乗っている人が誰かと立ち話をする際、立っている相手が2人、3人と増えるにつれて、視線の高さが合わず会話に入りにくくなったり見下されているような感覚になったりするという。海外では「ハグできない/しにくい」という機能面の問題がコミュニケーションを阻害することもある。「立ち上がること」が精神面に及ぼす好影響は、けして小さくないのだ。
「筑波大学での研究から生まれた中核技術を用いて、足の不自由な方の健康面、機能面、精神面へ貢献し、ひとりでも多くの人に、望めば立ち上がれて、潜在力を発揮できるようになる世界を目指しています」と江口氏は話す。
「ばね」で立ち上がりを支援する
ここからは、Qoloがどのような仕組みで起立を支援しているのかを見ていこう。
立って乗る車いすを開発したのは、Qoloが初めてというわけではない。有名なところでは、スウェーデンのペルモビールというメーカーの車いすがスタンディング機能を搭載している。ただ、そういうものはモーターで起立をアシストするものが多い。それらは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などのように進行性で全身が動かなくなる病気の患者の使用を想定しているためだ。使う人が自分で体を動かせる部分が少ないため、座る、寝る、立つなどさまざまなバリエーションの姿勢を車いすの側がサポートする必要がある。できることが多いぶん構造が複雑になり、価格も高くなる。
対して、Qoloの起立をアシストする機能には電気を使っておらず、機械的な仕組みで実現しているのが特徴的だ。ちなみに移動(走行)のための動力源は電気で、モーターで走り、手元のスティックで操縦する。
「多くの車いすユーザーは体を動かせる部分が残っています。動かせる部分を使いながら、いかに今までと同じような感覚で立ち上がれるか。私たちはそこに研究の意義を見いだしてやってきました」
Qoloが起立をアシストするのに用いているのは「ばね」である。より正確にいうと、圧縮されたガスの圧力を利用したガススプリングを使っている。自動車のハッチバックドアの開閉部などに使われる部品だ。反発力が強く、1本のガススプリングで100kg程度のものを持ち上げる反発力を持つものもある。

足の間に2本見えるのがガススプリングだ。座った状態の時はスプリングを圧縮した状態でロックする。立ち上がる時は、ロックを外すことでスプリングの伸びようとする力が解放される。すると、膝の部分にある回転軸を中心に膝を伸ばそうとする力が発生する。
それと同時に膝の回転軸まわりに座面が上がって立つ姿勢を支えるように動くので、胴体の傾きでバランスを取りながら立ち上がることができるのだ。シンプルな構造で動作も速い。逆に座る時は、座面に体重をかけながらスプリングを圧縮していく。
200万通りの設計をシミュレーション
出来上がったものを見ると簡単な仕組みのように思える。しかし江口氏は、「どのような力/特性を持つばねを使うか、それをどの位置に取り付けるかの調整が、実は難しい」と話す。さらに、乗る人の体の各部位の長さや重さ、どれくらい胴体を前や後ろに倒せるかによっても調整の仕方は違ってくる。
「いすに座っている人の額を指で押さえると立てなくなる話は有名ですが、まさにその話の通りで、立ち上がるためには最初に胴体を前へ倒す動作が必要です。その動きをきっかけに、お尻で荷重を支えていた状態から、足の裏で荷重を支える状態へシフトします。立ち上がる動作って、すごく複雑で奥が深いんです。この動きを、どうすれば人間らしい振る舞いで立たせられるかの研究に、かなり時間を使いました」
最初は、目指すべき立ち上がり方のモデルをコンピューター上で作った。障害を持っている人は胴体を前後に振れる幅が特に少なく、深く倒すと支え切れなくて倒れてしまうため、無理なく胴体を倒せる角度に収まるような立ち上がり方をモデル化した。
その後は、モデル通りの動きで立ち上がるためにはどのようなアシスト力が必要かを探っていった。ばね定数や反発力など、どのような特性を持ったスプリングを使うとよいのか。スプリングを車いすに取り付ける両端と、膝のところにある回転軸の3点の位置関係をどうすべきか。およそ200万通りの組み合わせをコンピューターでシミュレーションし、評価していったのだという。
 スプリングの反発力を適切な支援力に生かす設計を探った。
スプリングの反発力を適切な支援力に生かす設計を探った。
そうやって最適なパターンは見つかったものの、身長や体重は人によってバラバラだ。そのバリエーションに対応するため、ガススプリングの片方の取り付け位置をスライドして調整できるようにしたのが最新の試作機だ。
モビリティとしての気持ちよさを追求するフェーズへ
今回の取材で見せていただいた試作機は、会社設立後初めて作ったもので、2012年に筑波大学で研究を始めた時から数えると5台目だ。この試作機は、スプリングが伸びて立位になると、連動して後輪が前にスライドして前輪との幅が縮まる仕組みになっている。
 座位から立位になると、前輪と後輪の距離が縮まる。
座位から立位になると、前輪と後輪の距離が縮まる。
「この機構のおかげで、今までで一番小回りが利く試作機になりました。前までの試作機は車体が前後に長くて小回りが利かず、室内で使い物にならなかったのです。そのぶん安定性は高く、急な坂でも倒れず立って登れるほどでしたが、その必要性と室内での小回りとどちらが大事なのかを考える上で、今回の試作機では小回りのほうに振ってみた形です」
また、前の試作機は旋回するときの回転軸が乗っている人の頭の位置から離れていた。そのため、立位で旋回する時には振り回されるような状態になっていたのだ。そこで今回の試作機では、立っていても座っていても機体の旋回中心と頭の位置をほぼ同じにし、旋回する時は自分を軸に回っていると思えるような操縦体験を目指したのだという。
江口氏は、「それが良いのか悪いのかは、車いすユーザーに試乗してもらって検証しなければ」と慎重ながら、「自分が乗ってみた限りでは、前のモデルよりも相当操縦がしやすくなりました。日常生活で使うことを考えた時にどういう構成が良いのか、モビリティとしての使い勝手や快適さを追求する段階にようやく差し掛かってきた感じです」と評価する。
人はモビリティで自由を手に入れる
江口氏は、子どもの頃から自動車の開発エンジニアになりたいと思っていたそうだ。
「生まれ育ったのは埼玉で、自動車がないとどこにも行けないようなところだったので、バイクとか自動車は自由の象徴でした。手にすることでものすごく大きな力を持てる、みたいな。バイクや自動車を運転する楽しさの正体は何なのだろうと思いながら、それを再生産できるようなエンジニアになりたいと思ったんです」

中学卒業後は、高専の機械工学科へ進学。高専時代は、1Lのガソリンで自動車をどれだけ走らせられるかを競うエコランの部を立ち上げて活動したり、卒業研究では自動走行するロボットを作ったりもした。自動走行の研究は面白かったが、「モビリティから感じる自由や楽しさ」とは少し違う方向性だとも感じていた。
「人の身体能力を拡張し、自由で楽しい気持ちにさせるモビリティにはどのような要素が備わっているべきなのか」という疑問への答えは見つからないまま高専を卒業し、2011年に筑波大学へ3年生として編入する。
Qoloの研究を始めたのは、大学4年で配属された人工知能研究室でのことだった。江口氏は当初モビリティについて研究したいと考えていたが、研究室の鈴木健嗣教授から「気持ちよく動き回るモビリティ自体の研究は他でも多くされている。でも、そのもっと手前、人間が移動しようとする時にまず立ち上がる、そういう根源的なところから研究している人はあまりいない」という話をされたそうだ。
「ちょうどその頃、祖母が転んで骨折し、歩きづらくなってしまったんです。習い事もできなくなりましたし、家事を完璧にする人だったのですがそれもできなくなってしまった。その様子を見て、立ち上がれることは思っている以上に大きな意味があるのだと感じました」
そこから、立ち上がる動作をアシストする仕組みを卒業研究のテーマにして、現在のQoloの原型となるパーソナルモビリティの開発に取り組んでいった。
最初に作った試作機は、2014年に国際デザインコンテスト「ジェームズダイソンアワード2014」の国際選考で準優勝に輝いている。この時は、普通のいすに座った状態からの立ち上がりを支援し、立位でのみ移動できる座面がついていないパーソナルモビリティだった。
夢だった自動車エンジニアになるも期せずして再び研究の道へ
修士課程を修了した江口氏は、自動車メーカーにエンジニアとして就職した。立って乗る車いすの研究は区切りを付け、夢だった自動車エンジニアの道へ踏み出したのだ。
しかし3年経とうとした頃に転機が訪れる。修士課程の時に提出し、その後リバイスを続けていた論文が学術誌に受理されたのだ。これにより、筑波大学が社会人向けに設けている博士課程「早期修了プログラム」の審査要件が満たされた。このプログラムは、通常3年の博士課程を会社に勤めながら1年で修了できるもので、論文が受理されたのはこのプログラムのエントリー締め切り2週間前のことだった。
不意に訪れた事態。江口氏は「Qoloはやり残した部分がある。1年で成果としてまとめて、悔いのない形で研究を終わりにしよう」と考え、早期修了プログラムに飛び込んだ。
「自動車会社での仕事も楽しく、充実していました。でも大学で再びQoloに携わるようになると、自動車の開発とは違う楽しみがありました。また、実験に協力してくださる車いすユーザーの方たちとコミュニケーションを取っていく中で、『Qoloを本当に必要としてくれているんだ』と感じ、背中を押されているような気持ちも湧いていました」
そうして会社と大学、二足のわらじで1年間を過ごし博士号を取得した江口氏は、2019年春に会社を退職。筑波大学の研究員となった。
またその頃、トヨタ・モビリティ基金がイギリスのNPOであるNestaと実施するコンテスト「トヨタ・モビリティ・アンリミテッド・チャレンジ」に、筑波大学チームQoloとしてエントリーしていた。下肢まひ者の移動の自由に貢献する革新的な補装具の実現に向けたコンテストだ。世界中からエントリーがあった中、チームQoloは最終候補5チームの1つに選ばれ、製品化に向けた試作機の開発費用を勝ち取った。
 トヨタ・モビリティ・アンリミテッド・チャレンジにエントリーした3代目の試作機。
トヨタ・モビリティ・アンリミテッド・チャレンジにエントリーした3代目の試作機。
レンタルでの提供を想定、2026年にはアメリカでの展開も視野
「その後2年間は試作機をひたすら作りました。コロナ禍で大変な時期もありましたが、実験に協力してくださる被験者の方の裾野も広がりました。ここで自分が止めてしまうと終わりになってしまいますし、もう少し頑張ったら良いものになるんじゃないかというチームの空気もあって、2021年4月にQolo株式会社を設立しました」
江口氏が代表取締役を務め、現在は取締役2名、社外取締役1名という組織構成で、さらに医学、工学、事業開発の各専門家を社外のアドバイザーに迎えている。ほかアルバイト2名と、エンジニアリング系の試作や工業デザインなどの部分は業務委託でパートナーとともに開発を続けている。
2021年8月には、DEFTA Partnersと提携して6000万円の資金調達を実施したほか、広沢技術振興財団や厚生労働省などからの助成を受けている。また2022年9月には、日本貿易振興機構(JETRO)のスタートアップ企業海外進出支援プログラム「SCAP(Startup City Acceleration Program)」の参加企業として採択され、海外展開に向けた準備を進めている。
ビジネスとしては、初期製品は販売ではなくレンタルでの提供を考えている。最初は個人ユーザー向けではなく、医療機関や障害者を雇用する企業などを対象に想定しており、2023年後半のサービスインを目標としているそうだ。また、2026年度にはアメリカでの提供開始をマイルストーンに置き、さらなる改良を重ねていく予定だ。
初めは自動車やバイクからモビリティの「自由に動き回れる楽しさ」を感じて研究開発の道を歩き始めた江口氏。これからは、足の不自由な人たちのために「立ち上がって生活する自由を」という会社のビジョン実現を追い求めていく。
 筑波大学キャンパス内の産学リエゾン共同研究センター棟の一室がQoloのオフィス。緑豊かなキャンパスを試走することもあるそうだ。
筑波大学キャンパス内の産学リエゾン共同研究センター棟の一室がQoloのオフィス。緑豊かなキャンパスを試走することもあるそうだ。